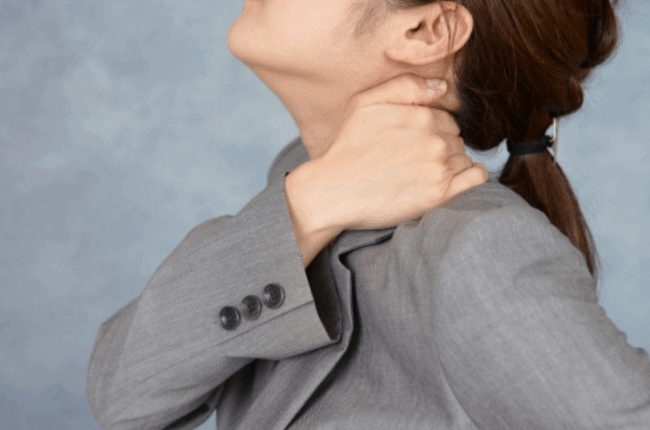カラダの不調の根本原因へのアプローチ
長年の施術経験で得たのは、目の前の「痛み」や「不調」にとらわれない、その奥に潜む根本原因を見極める視点です。
カラダは複雑な連鎖で成り立っています。たとえ一部分に不調を感じていても、その原因は予想外の場所にあることが少なくありません。まるで精密な歯車のように、カラダ全体の繋がりがどこか一か所でも妨げられると、バランスは大きく崩れてしまいます。
だからこそ徹底したカウンセリングと動作検査で、あなたの不調を多角的に深掘りします。単に症状を和らげるだけでなく、その背景にある真の原因を探し出すことを重視しています。さらに、40年以上の武道経験で培った**「身体を使いこなす」という深い理解**を、施術に活かすことで、理論だけでなく、自身の体で体得した「動きやすさ」や「バランス」感覚を、施術に応用するということです。
このブログでは、そうした経験と知識、そして武道から得た身体への洞察を交えて、どうすれば根本改善ができるかをお伝えしていきます。